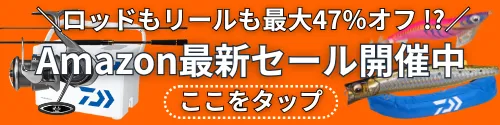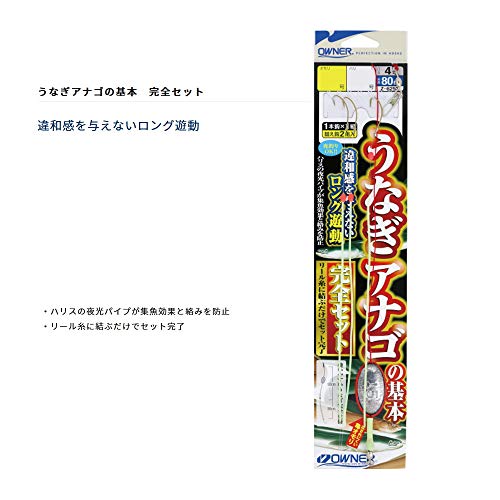ウナギ釣りに興味があるけれど、どんな仕掛けを選べば良いか迷っていませんか?
確かに釣具店に行くと様々な仕掛けが並んでいて、初心者の方には選択が難しいものです。でも実は、ウナギ釣りの仕掛けはそれほど複雑ではありません。
長年ウナギ釣りを楽しんできた経験から言うと、基本的な仕掛けさえ理解してしまえば、誰でも手軽にウナギ釣りを始められます。むしろシンプルな仕掛けの方がトラブルも少なく、釣果も安定するんです。
この記事では、初心者の方でも迷わず選べるおすすめ仕掛けから、自作方法、釣り場に合わせた使い分けまで、ウナギ釣り仕掛けの全てを詳しく解説します。

ウナギ釣り仕掛けの基本構成と必要なもの

ウナギ釣りを始める前に、まずは基本的な仕掛けの構成を理解しておきましょう。実際に現場で使ってみて感じるのは、複雑な仕掛けよりもシンプルな構成の方が圧倒的に使いやすいということです。
ウナギ釣りに必要な基本アイテム一覧
まず、ウナギ釣りに必要な基本アイテムをまとめてご紹介します。釣り初心者の方でも、これだけ揃えれば十分ウナギ釣りを楽しめますよ。
| アイテム | おすすめ仕様 | 用途・重要度 |
|---|---|---|
| 釣り竿 | 3〜4m、オモリ負荷15〜20号 | 投げ竿・万能竿(必須) |
| リール | スピニング3000〜3500番 | 糸付きが便利 |
| ウナギ針 | 11〜14号 | ウナギ専用設計・ハリス付き(必須) |
| オモリ | 中通し10〜15号 | 仕掛けを底まで沈める(必須) |
| サルカン | 5号前後 | 糸絡み防止(重要) |
これらのアイテムの中でも、特に重要なのはウナギ専用針です。普通の釣り針とは形状が違い、ウナギの細長い口に合わせて設計されています。実際に使ってみるとその違いがよく分かりますね。
ウナギ釣り仕掛けの2つの基本パターン
ウナギ釣りの仕掛けには、大きく分けて2つの基本パターンがあります。どちらも初心者の方でも簡単に使えるシンプルな構成です。
中通しオモリを使ったぶっ込み仕掛け(投げ釣り)
最もスタンダードで使いやすいのが、この中通しオモリを使った仕掛けです。仕掛けの構成がシンプルで、トラブルも少ないのが特徴ですね。
私も初めてウナギ釣りに挑戦した時は、この仕掛けから始めました。実際に河口の釣り場で使ってみたところ、投げやすくてアタリも分かりやすく、初心者には最適だと感じました。
仕掛けの基本構成は、道糸→中通しオモリ→サルカン→ハリス→針の順番になります。オモリが中通し式なので、ウナギがエサを食べる時に違和感を感じにくいのがメリットです。
・ウナギが餌を食べる時の違和感が少ない
・仕掛けが絡みにくい
・遠投しやすい
・初心者でも扱いやすい
ウキを使った仕掛け(河川・池向け)
流れが緩やかな河川や池では、ウキを使った仕掛けが効果的です。特に夜釣りでは電気ウキを使うことで、アタリが一目瞭然になります。
先月も地元の川でウキ仕掛けを使ってみましたが、薄暗くなってからウキがピカピカと光ってくれるおかげで、離れた場所からでもアタリが分かりました。
ウキ仕掛けの基本は、道糸→ウキ→オモリ→ハリス→針の構成です。タナ(水深)の調整がしやすく、底付近を正確に狙えるのが大きなメリットですね。
・アタリが視覚的に分かりやすい
・タナ調整が簡単
・流れの変化に対応しやすい
・夜釣りでも安心
おすすめウナギ釣り仕掛けランキング4選

これまで様々なウナギ仕掛けを試してきた経験から、実際に使って良かったものだけを厳選してランキング形式でご紹介します。価格と性能のバランス、使いやすさを重視して選びました。
がまかつ 糸付三越ウナギ|初心者に最適な仕掛け
信頼性抜群のがまかつ製で、初めてのウナギ釣りでも安心して使える定番仕掛けです。針の形状がウナギの口に最適化されており、バラシが圧倒的に少ないのが特徴ですね。
実際に近所の川で初心者の方にこの仕掛けを勧めることが多いのですが、皆さん「思った以上に使いやすい」と喜んでくれます。特に印象的だったのは針の鋭さで、ウナギがしっかりと餌を咥えてくれた時の針掛かりの良さに驚かされました。

ハリス4号、30本入りでコスパも良好。どんなウナギ釣り初心者の方にもおすすめできる、まさに鉄板の仕掛けです。
- ウナギ釣り初心者の人
- 信頼性の高いメーカー品を使いたい人
- コスパ重視で選びたい人
- 針掛かりの良さを重視する人
- バラシを減らしたい人
ささめ針 うなぎ・アナゴぶっこみ仕掛|コスパ抜群の定番品
価格の安さと実用性のバランスが素晴らしく、数をこなしたいウナギ釣りには最適な仕掛けです。オモリ付きの完成品なので、届いてすぐに使えるのも嬉しいポイントですね。
知人のベテランアングラーも「安いからといって侮れない」と評価しており、実際に先月の釣行でも安定した釣果を上げることができました。特にオモリの形状が底で転がりにくく設計されているのが印象的でした。

複数本セットする時や、根掛かりを恐れずに積極的に攻めたい釣り人におすすめです。
- コストを抑えてウナギ釣りを楽しみたい人
- 複数本の竿を同時に出したい人
- 根掛かりを恐れずに攻めたい人
- 完成仕掛けをすぐに使いたい人
- 予備仕掛けを多く持参したい人
オーナー 糸付でん助うなぎ|大型ウナギ対応の強力仕掛け
大型のウナギにも対応できる強度重視の仕掛けで、60cm超えの良型も安心してやり取りできます。ハリス5号の太さは一見オーバースペックに見えますが、実際に大きなウナギが掛かった時の安心感は格別です。
実際に地元の河口で使用した際、予想以上に大きなウナギが掛かりましたが、ハリスが切れることなくしっかりと取り込むことができました。特に印象的だったのは針の太軸設計で、大型ウナギのパワーにも十分耐えてくれる頼もしさを感じました。

大型のウナギが期待できるポイントや、確実に取り込みたい状況での使用におすすめです。
- 大型ウナギを狙いたい人
- バラシを絶対に避けたい人
- 強度重視で仕掛けを選びたい人
- 河口や下流域で釣りをする人
- 一発大物を狙いたい人
がまかつ ウナギ専用仕掛け|プロ仕様の高感度設計
プロの要求に応えるハイエンド仕掛けで、微細なアタリも逃さない高感度設計が特徴です。価格は少し高めですが、その分確実にウナギを仕留めたい時には欠かせない仕掛けですね。
ベテランアングラーに勧められて購入しましたが、正直、最初は半信半疑でした。しかし実際に使ってみると、針の食い込みの良さや、わずかなアタリでもしっかりと針掛かりしてくれる性能に驚かされました。

ワンランク上のウナギ釣りを目指したい、中級者以上の釣り人におすすめです。
- 本格的にウナギ釣りに取り組みたい人
- 微細なアタリを感じ取りたい人
- 品質重視で仕掛けを選びたい人
- 確実性を最優先したい人
- プロ仕様の道具を使いたい人
釣り場別ウナギ仕掛けの使い分け
長年ウナギ釣りをやってきて分かったのは、釣り場の環境に合わせて仕掛けを使い分けることの重要性です。同じ仕掛けでも、場所が変われば全く結果が違ってくるんですね。
河口・汽水域でのウナギ仕掛け
河口域は最もウナギの数が多いポイントですが、潮の流れと塩分による厳しい環境に対応した仕掛け選びが重要になります。
潮の流れに対応した重めのオモリ選択
河口域では潮の流れが強く、軽いオモリでは仕掛けが流されてしまいます。実際に地元の河口で釣りをしていると、15号以上のオモリでないと底を維持できないことが多いですね。
| 潮の強さ | おすすめオモリ重量 | 使用場面 |
|---|---|---|
| 弱い流れ | 10〜12号 | 満潮前後、穏やかな日 |
| 中程度の流れ | 12〜15号 | 通常時、一般的な河口 |
| 強い流れ | 15〜20号 | 大潮時、流れの速い河口 |
私の場合、河口では基本的に15号のオモリを使い、流れが特に強い日は20号まで重くすることもあります。
塩分に強いハリス素材の重要性
河口域では塩分による腐食が進みやすく、耐塩性の高いフロロカーボンハリスを選ぶのがおすすめです。ナイロンハリスだと数時間で劣化してしまうことがあるんですね。
実際に同じ日にナイロンとフロロカーボンを比較してみたところ、フロロの方が明らかに長持ちしました。価格は少し高くなりますが、大型ウナギとのやり取りでは安心感が全然違います。
河川中流・下流域でのウナギ仕掛け
河川の中流から下流域は、流れの変化が激しく、障害物も多い環境です。そのため、状況に応じて柔軟に対応できる仕掛けが必要になりますね。
流れの変化に対応した仕掛け調整
河川では雨の影響で水位や流れが大きく変わります。晴れた日と雨上がりでは、全く違う仕掛けが必要になることも多いんです。
雨上がりの河川中流域で釣行
普段使っている10号オモリでは底が取れない状況
根掛かり対策の仕掛け工夫
河川では沈木や岩などの障害物が多く、根掛かり対策が重要です。私がよく使うのは、捨てオモリシステムと呼ばれる方法ですね。
これは、オモリだけが根掛かりした時に、オモリを切り離して針とハリスを回収できる仕組みです。実際にこの方法を使うようになってから、仕掛けのロスト率が大幅に改善しました。
上流・渓流域でのウナギ仕掛け
上流域や渓流は、水が澄んでいてウナギに警戒されやすい環境です。そのため、より繊細な仕掛け作りが求められますね。
狭い場所での短竿仕掛けセッティング
渓流では取り回しを考えて、2.5m程度の短い竿を使うことが多いです。そのため、仕掛けもコンパクトにまとめる必要があります。
ハリスは30cm以下に抑え、オモリも必要最小限の重さにするのがコツです。実際に山間部の小さな川で試してみたところ、コンパクトな仕掛けの方がウナギの食いも良くなりました。
清流向けの軽量仕掛け
清流では8号以下の軽いオモリを使い、ウナギに違和感を与えないような軽やかな仕掛けを心がけています。
また、ハリスも2.5号程度の細いものを使用し、針も小さめの10号を選ぶことが多いです。このような繊細な仕掛けにすることで、警戒心の強い上流のウナギにもアプローチできるようになりました。
ウナギ釣り仕掛けの自作方法と作り方
市販の仕掛けも便利ですが、自分で作った仕掛けの方が釣り場に合わせて細かく調整できるのが魅力です。作り方も思っているより簡単で、一度覚えてしまえば現場でも素早く作れるようになりますよ。
中通しオモリ仕掛けの作り方手順
最もスタンダードで使いやすい中通しオモリ仕掛けの作り方を、ステップごとに詳しく解説します。初心者の方でも15分程度で完成させることができますよ。
必要な材料と道具
仕掛け作りに必要な材料と道具をまとめました。全て釣具店で手軽に購入できるものばかりです。
| 材料・道具 | 推奨仕様 | 価格目安 |
|---|---|---|
| 中通しオモリ | 10〜15号 | 200〜300円/5個 |
| サルカン | 5号 | 150〜250円/10個 |
| ハリス | フロロ3〜4号 | 300〜500円/50m |
| ウナギ針 | 11〜12号 | 400〜600円/20本 |
| ハサミ | フィッシングハサミ | 500〜1000円 |
特に重要なのはハリス用のフロロカーボンラインです。ナイロンより若干高いですが、耐久性と感度を考えると間違いなくフロロをおすすめします。
結び方のコツと注意点
【道糸にオモリを通す】
中通しオモリに道糸を通します。向きを間違えないよう、細い方から通すのがコツです。
【サルカンを結ぶ】
道糸の先端にサルカンをクリンチノットで結びます。5回以上巻くと強度が安定します。
【ハリスを作る】
ハリス用の糸を40cm程度カットし、片方にウナギ針を結び、もう片方にサルカンを結びます。
【仕掛けを接続】
道糸側のサルカンとハリス側のサルカンを接続して完成です。
結び方で最も重要なのは、結び目をしっかりと湿らせてから締め込むことです。乾いたまま締めると糸が傷んで強度が落ちてしまいます。実際に現場で仕掛けを作る時も、必ず水で湿らせてから結ぶようにしています。
ウキ仕掛けの作り方手順
流れの緩い河川や夜釣りで活躍するウキ仕掛けの作り方も、基本を覚えれば簡単です。アタリが目で見て分かるので、初心者の方にもおすすめの仕掛けですよ。
電気ウキを使った夜釣り仕掛け
夜釣りでは電気ウキを使った仕掛けが絶対におすすめです。暗闇でもアタリが一目瞭然で、離れた場所からでも状況が把握できます。
電気ウキの取り付けは、ウキ止め糸を使って好きな位置に固定できます。実際に使ってみると、ウナギがエサを咥えた瞬間にウキがスッと沈むので、合わせのタイミングが非常に分かりやすいですね。
・ウキ止め糸で深さを調整
・電池は予備を必ず持参
・ウキの浮力に合わせたオモリ選択
・夜間の視認性を最優先
タナ設定と調整方法
ウキ仕掛けで重要なのは正確なタナ設定です。ウナギは底にいる魚なので、針が底から5cm程度浮いた状態がベストポジションですね。
タナの測り方は、まず重めのオモリを付けて底を確認し、その後ウキが少し沈む程度のオモリに交換します。この作業を丁寧に行うことで、確実にウナギのいるレンジを攻めることができます。
ペットボトル仕掛けの作り方
コストをかけずに複数本の仕掛けを展開したい時に便利なのが、ペットボトル仕掛けです。材料費はほぼ0円で、効果は市販品と遜色ありません。
コスト0円で作れる簡単仕掛け
ペットボトル仕掛けに必要なのは、空のペットボトル(500ml角型がおすすめ)、道糸、オモリ、針だけです。作り方も非常にシンプルで、30分もあれば3〜4セット作れてしまいます。
ペットボトルには5分目程度水を入れ、首の部分に道糸を結びます。道糸はペットボトルの胴体部分に巻き付けて保管し、先端にオモリと針を付けて完成です。
複数本同時展開のメリット
ペットボトル仕掛けの最大のメリットは、複数本を同時展開できることです。ウナギは時合いが短いので、できるだけ多くのポイントを同時に攻めた方が効率的なんですね。
実際にペットボトル仕掛けを5本展開して釣りをしたことがありますが、それぞれ違うポイントにセットしておくことで、ウナギの居場所を効率よく探ることができました。ペットボトルが倒れたらアタリの合図なので、遠くからでも分かりやすいのも助かります。
ウナギ釣り仕掛けを選ぶときに絶対見るべき5つのポイント
これまでの経験から、仕掛け選びで失敗しないための重要なポイントを5つに絞ってお伝えします。この5つさえ押さえておけば、どんな釣り場でも適切な仕掛けを選べるようになりますよ。
針のサイズと形状選び
ウナギ釣りの成功を左右する最も重要な要素が針選びです。針が合わないと、どんなに良いポイントでも釣果に繋がりません。
ウナギ専用針の特徴と選び方
ウナギ専用針は普通の釣り針とは明らかに形状が違います。細長くて先端が鋭く、ウナギの細い口にも確実に刺さるように設計されているんです。
実際に普通の丸セイゴ針とウナギ針を比較してみたところ、ウナギ針の方がはるかにフッキング率が高いことを実感しました。特に印象的だったのは、ウナギが餌を飲み込んだ時の針掛かりの確実性で、バラシが大幅に減りました。
| 針の種類 | 特徴 | 適用場面 |
|---|---|---|
| ウナギ針(細軸) | 食い込み抜群、小型向け | 活性が低い時、小型中心 |
| ウナギ針(太軸) | 強度重視、大型対応 | 大型狙い、パワーファイト |
| アナゴ針 | ウナギ針より短め | 餌持ちを重視する時 |
餌に合わせた針サイズの使い分け
使用する餌によって最適な針サイズが変わるのも、ウナギ釣りの奥深いところです。餌が大きければ針も大きく、小さければ針も小さくするのが基本ですね。
例えば、アオイソメを使う時は11〜12号、大きめのミミズやキビナゴを使う時は13〜14号を選ぶことが多いです。実際に餌に合わせてサイズを変えるようになってから、明らかに食い込みが良くなりました。
ハリスの太さと長さ設定
ハリス選びは、強度と感度のバランスが重要です。太すぎると警戒され、細すぎると切れてしまうというジレンマがあるんですね。
根掛かりと強度のバランス
ウナギ釣りでは根掛かりが付き物なので、ある程度の強度は必要です。しかし、強度を重視しすぎて太いハリスにすると、今度はウナギに警戒されてしまいます。
私の経験では、3〜4号のフロロカーボンハリスが最もバランスが良いと感じています。これより細いと大型ウナギに切られるリスクが高く、太いと食いが明らかに落ちてしまうんです。
根掛かりの多いテトラ帯での釣行
3号に変更すると一気にアタリが増加
ウナギのサイズ別ハリス選択
狙うウナギのサイズによってハリスの太さを調整するのも重要なテクニックです。小型中心なら3号、大型狙いなら4〜5号という使い分けをしています。
ハリスの長さについては、30〜50cmが基本ですが、根掛かりが多い場所では短めに、警戒心の強いウナギには長めに設定することもあります。
オモリの重さと形状
オモリ選びは釣果に直結する重要な要素です。重すぎても軽すぎても、ウナギの食いに悪影響を与えてしまうんです。
釣り場の流れに合わせた重量選択
オモリの重さは、釣り場の流れの強さで決まります。底をキープできる最低限の重さを選ぶのがコツですね。
| 釣り場環境 | 推奨オモリ重量 | 使用場面 |
|---|---|---|
| 池・沼 | 6〜8号 | 流れがほとんどない場所 |
| 河川上流 | 8〜10号 | 軽い流れがある清流 |
| 河川中下流 | 10〜15号 | 一般的な河川 |
| 河口・汽水域 | 15〜20号 | 潮流の影響がある場所 |
実際に現場では、まず軽めのオモリで底を確認し、流されるようなら徐々に重くしていく方法を取っています。
根掛かり回避のオモリ形状
オモリの形状も根掛かり率に大きく影響します。丸型よりも偏平したナス型やお多福型の方が底で転がりにくいのでおすすめです。
特にお多福型は根掛かり回避性能が高く、岩やテトラの隙間に入りにくい形状になっています。実際に使い比べてみると、その差は歴然としていました。
サルカンとスナップの役割
地味な存在ですが、サルカンとスナップは仕掛けの要となる重要なパーツです。品質の悪いものを使うと、思わぬところで破損してしまうんですね。
仕掛け交換の効率化
サルカンやスナップを適切に使うことで、現場での仕掛け交換が格段に早くなります。特に夜釣りでは、この効率化が釣果に直結することも多いです。
私はハリス部分にはサルカンを使い、オモリ部分にはスナップを使うことが多いです。この組み合わせにより、オモリだけを素早く交換したり、ハリス部分だけを新しいものに変えたりできるようになります。
糸絡み防止の工夫
サルカンの最も重要な役割は糸絡み防止です。サルカンがないと道糸とハリスが絡んで、せっかくの仕掛けが台無しになってしまうことがあります。
特にウナギ釣りでは長時間仕掛けを放置することが多いので、サルカンの回転性能が重要になります。安物だと回転しなくなって、結局糸絡みを起こしてしまうんですね。少し高くても、信頼できるメーカーのものを選ぶことをおすすめします。
夜釣り対応の視認性
ウナギ釣りは夜釣りがメインなので、暗闇でも状況が把握できる視認性が非常に重要になります。
ケミホタルと電気ウキの活用
夜釣りでのアタリ判断には、ケミホタルや電気ウキが欠かせません。光でアタリを知らせてくれるので、複数本の竿を出していても状況が一目で分かります。
私がよく使うのは、竿先にケミホタルを付ける方法です。ウナギがエサを咥えると竿先が動いて、ケミホタルの光が揺れるのですぐに分かります。電気ウキと併用することで、さらに確実性が高まりますね。
・ケミホタルは予備を多めに持参
・電気ウキの電池残量確認
・蛍光色のラインマーカー活用
・ヘッドライトは必須装備
暗闇でのアタリ判断方法
暗闇でのアタリ判断は慣れが必要ですが、コツを掴めば昼間以上に集中して釣りができるようになります。視覚だけでなく、音や振動も重要な情報源になるんです。
例えば、竿に鈴を付けておくと、わずかなアタリでも音で知らせてくれます。また、竿を手で軽く触れていると、ウナギが餌を咥えた時の微細な振動も感じ取れるようになります。
ウナギ釣り仕掛けのよくある失敗と対策
長年ウナギ釣りをやってきて、よくある失敗パターンとその対策を知っておくことの大切さを痛感しています。同じ失敗を繰り返さないよう、代表的なトラブルと解決方法をご紹介しますね。
根掛かりが多すぎる場合の対処法
根掛かりはウナギ釣りの宿命とも言えるトラブルですが、適切な対策により大幅に減らすことができます。
まず重要なのは、オモリの形状を見直すことです。丸いオモリは転がりやすく根掛かりの原因になるので、偏平したお多福型に変更してみてください。実際にこの方法で、根掛かり率を半分以下に減らすことができました。
また、投入ポイントを少しずつずらして、底の状況を把握することも大切です。一度根掛かりした場所は避けて、周辺の少し浅い場所を狙うだけでも効果があります。
・お多福型オモリの使用
・投入ポイントの工夫
・軽めのオモリで底質確認
・捨てオモリシステムの採用
アタリはあるのに針掛かりしない原因
「アタリはあるのに針掛かりしない」という状況は、ウナギ釣りで最もストレスが溜まるトラブルの一つです。原因の多くは針のサイズや餌の付け方にあります。
針が大きすぎる場合、ウナギが餌を咥えても針まで飲み込めずにバレてしまいます。逆に小さすぎると、しっかり掛からずに抜けてしまうんです。餌のサイズに対して針が適切かどうか、もう一度見直してみてください。
また、餌の付け方も重要です。針先が完全に隠れるように餌を付けるのがコツで、針先が出ているとウナギが警戒してしまいます。
仕掛けが絡む原因と予防策
仕掛けの絡みは時間のロスに繋がり、特に時合いの短いウナギ釣りでは致命的です。原因の大部分はキャスト時の糸の出方にあります。
予防策として最も効果的なのは、キャスト前に糸の出を確認することです。スプールから糸がスムーズに出るか、ガイドに絡みがないかをチェックしています。また、風の強い日は特に注意が必要で、風下に向かってキャストするようにしています。
ウナギ以外の魚ばかり釣れる時の調整方法
ハゼやセイゴなどの外道ばかり釣れて、肝心のウナギが釣れない時があります。餌の種類や針のサイズを調整することで、ウナギの確率を上げることができます。
外道が多い時は、虫餌から身餌に変更するのが効果的です。サバやイワシの切り身は餌持ちが良く、小魚に取られにくいんです。また、針も一回り大きくすることで、小型の外道を避けられます。
| 状況 | 対策 | 期待効果 |
|---|---|---|
| ハゼが多い | 針を大きく、餌を身餌に | 小型魚の回避 |
| セイゴが多い | タナを底べったりに | 中層の魚を避ける |
| フグが多い | 硬い身餌、太い針 | 餌取り対策 |
ウナギ釣り仕掛けと合わせて揃えたい必要なもの
仕掛けが決まったら、次はウナギ釣りに必要な道具一式を揃えましょう。どれも重要な役割があり、一つでも欠けると釣りが成り立たなくなってしまいます。
竿とリールの選び方
ウナギ釣りでは、高価な道具は必要ありません。むしろ、複数本用意して効率よく探る方が釣果に繋がります。
投げ竿とスピニングリールの組み合わせ
基本となるのは3〜4mの投げ竿と、3000番台のスピニングリールの組み合わせです。オモリ負荷15〜20号の竿であれば、どんなメーカーでも十分使えます。
私が使っているのも5000円程度のセット竿ですが、これまで何の問題もなく使えています。実際に高級竿と比較してみても、ウナギ釣りに限っては大きな差を感じませんでした。
・投げやすい3〜4m長
・オモリ負荷15〜20号対応
・スピニングリール3000番台
・複数本揃えることを優先
初心者向けセット竿の活用
釣具店で売られているセット竿は、ウナギ釣り入門には最適です。竿、リール、道糸がセットになっており、届いたその日から釣りを始められます。
特におすすめなのは、投げ釣り用のセット竿です。ウナギ釣りに必要な機能がすべて揃っており、価格も手頃なので、複数セット購入しても負担になりません。
餌の種類と使い分け
ウナギ釣りの成功は、餌選びにかかっていると言っても過言ではありません。釣り場の環境に合わせて適切な餌を選択することが重要です。
万能餌のアオイソメとミミズ
最も汎用性が高いのは、海ならアオイソメ、淡水ならミミズという使い分けです。迷った時はこの基本に立ち返ることをおすすめします。
アオイソメは動きが良く、ウナギの注意を引きやすいのが特徴です。一方、ミミズは匂いが強く、遠くからでもウナギを寄せる効果があります。どちらも釣具店で手軽に購入できるのも魅力ですね。
| 餌の種類 | 特徴 | 最適な環境 |
|---|---|---|
| アオイソメ | 動きが良い、活性向上 | 海・汽水域 |
| ミミズ | 匂いが強い、集魚効果 | 淡水域 |
| サバ切り身 | 餌持ち抜群、外道に強い | 外道が多い場所 |
| テナガエビ | 大型ウナギに特効 | 河川中下流域 |
特効餌の使い分けポイント
基本の餌で反応がない時は、その釣り場ならではの特効餌を試してみることをおすすめします。地域によって効果的な餌が違うのも、ウナギ釣りの面白さの一つです。
例えば、テナガエビが多い川ではテナガエビ、小魚が多い場所では小魚の切り身が効果的です。現地で手に入る餌を使うことで、思わぬ釣果に恵まれることもあります。
その他の必要な道具類
仕掛けと餌以外にも、ウナギ釣りに欠かせない道具がいくつかあります。これらを忘れると、現場で困ることになるので注意が必要です。
バケツ・タオル・ハサミの重要性
特に重要なのが、水汲みバケツ、タオル、ハサミの3点セットです。ウナギはヌメリが強く、素手では扱いにくいので、これらの道具が必須になります。
ハサミは仕掛けを切る時だけでなく、ウナギが針を飲み込んでしまった時にも使用します。無理に針を外そうとするとウナギを傷めてしまうので、糸を切って逃がす判断も大切です。
・水汲みバケツ(8L以上推奨)
・タオル(厚手のものを複数枚)
・フィッシングハサミ
・クーラーボックス
・ヘッドライト
夜釣り装備と安全対策
ウナギ釣りは夜釣りがメインなので、安全装備は絶対に軽視できません。特にヘッドライトとライフジャケットは必須です。
ヘッドライトは両手が自由になるタイプがおすすめで、予備電池も必ず持参してください。また、水辺での釣りにはライフジャケット着用が基本です。万が一の事故を防ぐためにも、安全対策は怠らないようにしましょう。
さらに、夜釣りでは虫除けスプレーや長袖の服装も重要です。蚊に刺されながらの釣りは集中力を削がれるので、しっかりと対策しておくことをおすすめします。
ウナギ釣りのマナーと注意点
ウナギ釣りを楽しむ上で、マナーと注意点を守ることは非常に重要です。特に以下の点に注意してください。
・地域の禁漁期間や規制を必ず確認
・釣り場の清掃と騒音対策
・小型ウナギ(40cm以下)のリリース
・私有地への無断立ち入り禁止
・夜釣りでの近隣住民への配慮
今回ご紹介したウナギ釣り仕掛けの知識を活用して、ぜひ天然ウナギの美味しさを味わってみてください。自分で釣ったウナギの蒲焼きは格別の美味しさですよ。基本をしっかりと押さえて、安全に楽しいウナギ釣りライフを送りましょう!