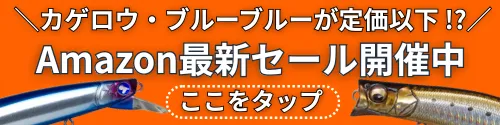シーバスルアーのカラー選びで迷った経験はありませんか?
同じポイントで釣りをしていても、カラーを変えただけで急に釣れ始めることがありますよね。
結論、シーバス釣りで最も汎用性が高く効果的なカラーはゴールドとナチュラル系の2色です。この2つがあれば、ほとんどの状況に対応できます。
長年シーバス釣りをやってきた経験から言うと、カラー選択は確実に釣果に影響します。ただし、闇雲に色を変えるのではなく、時間帯や水質などの条件に合わせた選択が重要なんです。
この記事では、科学的根拠(異なる背景色におけるスズキのルアー色の選択)に基づいたカラー効果から実践的な使い分け方法まで、シーバス釣りで本当に使えるカラー選択術をお伝えします。

シーバスが反応するカラーの科学的根拠を解説

シーバスルアーのカラー選択を語る前に、まずシーバスがどのように色を認識しているのかを理解することが重要です。
実際に釣り場でカラーローテーションをしていると、明らかに反応が変わる場面に遭遇します。これには科学的な根拠があるんです。
シーバスの視覚特性と識別できる色の波長域
鹿児島大学の研究結果「異なる背景色におけるスズキのルアー色の選択」によると、シーバスは551nmから609nmをピークに2峰性の応答を示すことが分かっています。
これを分かりやすく言うと、シーバスは青や緑の波長域に強く反応し、赤色系(638nm以上)への反応は著しく低くなります。
長年の釣行経験でも、確かにチャート系やブルー系のルアーに対する反応が良い場面を多く経験してきました。特に活性が高い時間帯では、この傾向が顕著に現れます。
また、シーバスはC型細胞と呼ばれる色覚細胞を持っているため、人間と同様に色を識別する能力があると考えられています。ただし、人間とは見える色の範囲が異なるということですね。
水深と濁りによる光の透過率がカラー効果に与える影響
水中では深度が増すにつれて、特定の波長の光が吸収される現象が起こります。
| 水深 | 透過しやすい色 | 透過しにくい色 |
|---|---|---|
| 表層(0-3m) | 全色域 | なし |
| 中層(3-10m) | 青・緑・黄色 | 赤・オレンジ |
| 深層(10m以深) | 青のみ | 赤・オレンジ・黄色・緑 |
私がよく釣りをする大河川では、水深5〜8mのレンジを攻めることが多いのですが、実際にブルー系やグリーン系のルアーの方が明らかに反応が良いことを実感しています。
また、濁りが入った場合はさらに複雑になります。泥やプランクトンなどの浮遊物により光が散乱し、視覚情報そのものが魚に届きにくくなるんです。
こうした条件下では、シーバスは側線や嗅覚など視覚以外の感覚に頼る傾向が強くなると考えられています。
夜間におけるシルエット効果とコントラストの重要性
夜釣りがメインのシーバス釣りでは、シルエット効果とコントラストが非常に重要になります。
魚の腹が白い理由をご存知でしょうか?これは下から見上げた時に太陽光と馴染んで見えにくくする保護色の役割があるんです。
夜間でも、光量によってカラー戦略は大きく変わります。新月など真っ暗な条件ではチャート系が最も視認性が高く、シーバスに存在をアピールできます。一方、満月や常夜灯下ではクリア系やブラック系のナチュラルアプローチが効果的です。
先月、地元の河口で新月の夜に釣りをした際の話です
チャート系に変更した途端、1投目でヒット
一方で、常夜灯や満月など光がある条件では、クリア系の光透過効果やブラック系のシルエット効果も有効になります。過度なアピールは逆にスレの原因となるため、ナチュラルなアプローチが重要です。
4つの基本カラー系統と効果的な使い分け方法

シーバスルアーには無数のカラーが存在しますが、基本となる4つの系統を理解すれば迷うことはありません。
これまで様々なカラーを試してきましたが、結局のところこの4系統の組み合わせで大部分の状況に対応できます。
ナチュラル系はイワシ・ボラパターンの基本カラー
ナチュラル系カラーは、ベイトフィッシュに似せた控えめなカラーの総称です。
代表的なのは、ブルーやシルバーを基調としたイワシカラー、ボラカラーなどです。また、蛍光ではない緑色やブラウンなどの自然界にありふれた色もこの系統に含まれます。
メリット:目立ちすぎず警戒されにくい、スレにくい
デメリット:魚に気付いてもらいにくい場合がある
実際の釣り場では、ベイトが豊富な状況や魚の活性が高い時間帯に威力を発揮します。特にデイゲームでのイワシパターンには欠かせないカラーですね。
地元の湾奥エリアでは、春から夏にかけてイワシの群れが入ることが多いのですが、そんな時はシルバー系のナチュラルカラーが最も効果的です。
アピール系はチャート・ゴールドで積極的にアプローチ
アピール系カラーは、派手で目立つカラーの代表格です。
黄色やピンク、オレンジといった蛍光色(チャートカラー)や、ゴールド系がこれに該当します。自然界にはまず存在しない色合いで、強烈にアピールします。
| メリット | デメリット |
|---|---|
魚に気付かれやすい ハマると大爆発する 濁り潮に強い | スレやすい 使える状況が限られる 警戒されやすい |
ゴールド系は特に濁った水に強いとされており、大雨の後の河口や都市部の港湾など、万年濁っているような場所で活躍します。
釣り仲間とよく話すのですが、アピール系は「当たれば大きい」カラーという印象です。特に朝夕マズメの短時間勝負では、積極的に使っていきたいカラーですね。
クリア系はスレ対策の万能カラー
クリア系カラーは、透き通った配色で存在感の薄さが最大の武器となります。
完全に透明なフルクリアから、チャート系の透けたカラーまで幅広く存在します。光を透過するため、ルアーのシルエットをぼやけさせ、小さく見せる効果があります。
これまでの経験で言うと、周りが釣れていない厳しい状況に最も強いカラーだと感じています。
実際に激戦区である地元の人気ポイントでは、クリアカラーでしか反応しない魚も多く経験しています。特に満月の夜や常夜灯周りでは欠かせないカラーです。
ブラック系は夜間の最強シルエットカラー
ブラック系カラーは、数あるカラーの中でも最も水中で目立つカラーです。
シルエットがハッキリするため、どんな色のルアーを投げても釣れない時の最終兵器的な存在です。特に夜釣りでは絶大な効果を発揮します。
| 状況 | 効果の理由 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| 満月のナイトゲーム | ナチュラルなシルエットを演出 | ★★★★★ |
| バチ抜けシーズン | 波動に頼らずシルエットで見せる | ★★★★★ |
| 夜光虫発生時 | 濁りの中でもくっきり見える | ★★★★☆ |
興味深いのは、ブラックは目立つのにスレに強いという点です。これは過剰なフラッシングをせず、シルエットだけでアピールするためだと考えられています。
特にブラピン(ブラック×ピンク)と呼ばれるカラーは、バチ抜けシーズンの定番として多くのアングラーに愛用されています。
時間帯別に見る効果的なカラー選択術

シーバス釣りにおいて、時間帯によるカラー選択は釣果を大きく左右します。
これまで朝から夜まで通しで釣りをする機会が多かったのですが、同じポイントでも時間とともにヒットカラーが変わることを何度も経験してきました。
朝夕マズメはゴールド・オレンジ系で活性の高い魚を狙撃
朝夕マズメは魚の活性が最も高まる時間帯で、ルアーを見つけてもらえれば高確率で口を使ってくれます。
この時間帯では、魚に見つけてもらいやすいアピール系のカラーが効果的です。特にゴールド系やオレンジ系は朝夕の光に美しく反射し、魚の捕食スイッチを入れてくれます。
地元河口での朝マズメ釣行
朝日が昇り始めた瞬間、ゴールド系に変更すると連続ヒット
ただし、その日の状況が悪くアピール系で口を使ってくれない時や、スレてしまった場合には、アピール力が控えめなコットンキャンディカラーも有効です。
コットンキャンディは七色の虹のような光を再現したカラーで、一見派手に見えますが実はアピール力は適度に抑えられています。
デイゲームはホロ・シルバー系のフラッシングでアピール
完全に日が昇った明るい時間帯には、ナチュラル系やクリア系のカラーが基本となります。
特にイワシを捕食している青物やシーバスを狙う際には、銀粉カラーと呼ばれるラメのようなカラーが強いとされています。強いフラッシングで太陽光を反射し、ベイトフィッシュを演出します。
| ベイトの種類 | おすすめカラー | 理由 |
|---|---|---|
| イワシ・アジ | 銀粉・シルバーホロ | ベイトの体色に最も近い |
| シラス | クリア・フルクリア | 透明感のあるベイトを表現 |
| ボラ | チャート・ゴールド | 大型ベイトの存在感を演出 |
実際の釣り場では、ベイトの種類に合わせてカラーを選択することで、格段に釣果が向上します。昼間でも水質が濁っている時には、コットンキャンディのアピール力が大活躍することもあります。
ナイトゲームは光量に合わせた3段階のカラー戦略
夜釣りでは、光量の違いによってカラー選択を3段階に分けることが重要です。
満月や常夜灯で明るい時と、新月など真っ暗な時では、まったく異なるアプローチが必要になります。
常夜灯・満月エリアはクリア系・ブラック系でナチュラルアプローチ
明るいナイトゲームエリアでは、クリア系やブラック系でナチュラルなシルエットを演出することが基本戦略となります。
特にクリア系は、光がルアーのボディを透過するため、満月や常夜灯の光を活かしたナチュラルな誘いができるのが最大の強みです。透明感のあるボディが水中で自然な小魚を演出してくれます。
満月の夜や常夜灯下では、魚の視界がクリアになるため、過度にアピールするカラーは警戒されやすくなります。そこでクリア系の透明感やブラック系の自然なシルエットが威力を発揮するのです。
常夜灯周りでは、光の境界線付近でクリア系とブラック系の使い分けが効果的です。明部ではクリア系の透明感を活かした自然なアプローチ、暗部ではブラック系の存在感のあるシルエットといった二面性を持たせることができます。
満月の日は魚の警戒心が高まるため、「いかに自然に見せるか」が勝負の分かれ目になります。クリア系なら光を透過させて本物の小魚のような透明感を、ブラック系なら、どんなに明るい夜でも違和感なく小魚のシルエットを演出できるのが強みですね。
新月・真っ暗なエリアはチャート・レッドヘッドでアピール勝負
新月や街灯のない釣り場など、真っ暗な条件ではチャート系やレッドヘッドの強力なアピールが最も力を発揮します。
真っ暗な状況では、魚にルアーの存在を知らせることが最優先となります。チャート系は暗闇でも視認性が高く、シーバスに「何かいる」ことを効果的に伝えられるカラーです。

特に、チャートとピンクが組み合わされたチャートピンクカラーは、バチ抜けシーズン(2月から6月頃)の暗い夜に強いとされており、この時期はタックルボックスに必ず入れておきたいカラーです。
水質・天候条件が変えるカラー効果の法則

水質や天候は、ルアーカラーの効果を大きく変える重要な要素です。
同じポイントでも、前日の雨で濁りが入っただけでヒットカラーが激変することを何度も経験してきました。
澄潮時は警戒心を解くナチュラル・クリア系の使い方
水の透明度が高く、ルアーが見えやすい時にはナチュラル系カラーやクリア系が基本のカラーになります。
澄潮時にアピール系カラーを選んでしまうと、目立ちすぎて警戒されたり、スレやすくなってしまうため注意が必要です。
ルアーがよく見える条件では、「いかに魚に違和感を与えないか」が重要になります。ベイトフィッシュに近い自然な色合いで警戒心を解くことを心がけましょう。
特に水の透明度が高い釣り場で晴れている日には、クリア系にしか反応しないといったことも珍しくありません。
また、レッドヘッドは水の透明度が高い場所でのナイトゲームに強いカラーとして知られています。頭部の赤がエラのように見えるという説もあり、ナチュラルでありながら適度なアクセントを加える絶妙なカラーです。
濁り潮時はゴールド・ブラック系で強烈アピール
水が濁っている時の定番カラーとなるのが、ゴールド系とブラック系です。
ゴールド系の反射は濁りの中でも強烈にアピールしてくれます。アカキンやグリキンなど、ゴールド系が組み合わされた色のルアーは濁り潮の強い味方です。
| 濁りの程度 | 第1選択 | 第2選択 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 軽い濁り | ゴールド系 | チャート系 | 反射とアピールのバランス |
| 強い濁り | ブラック系 | マットチャート | シルエット重視 |
| 激濁り | ブラック系 | 大型ルアー | 視覚以外の感覚に訴求 |
濁った河口付近などでボラを捕食しているシーバスがいる時には、昼間であってもチャート系カラーが強いとされています。これは大型ベイトの存在感を演出するためです。
夜間に加えて水が濁っているという極限にルアーが見えにくい状況では、ブラック系のシルエット効果が最も頼りになります。
晴天時は光量豊富な条件でのフラッシング系活用法
水中にたくさんの光が降り注ぐ晴れの日には、ナチュラル系やクリア系などの控えめなカラーを使うのが基本です。
特にイワシやアジなどのベイトフィッシュを盛んに捕食しているようであれば、銀粉カラーや銀メッキなどでキラキラとアピールさせるのが効果的です。
シルバーをベースとしたカラーは、晴れの日に使いたい万能なカラーですね。太陽光を効率よく反射し、ベイトフィッシュの鱗のきらめきを忠実に再現してくれます。
快晴の港湾エリアでのデイゲーム
シルバーホロに変更すると、自然なフラッシングで連続ヒット
曇天・雨天時は光量不足を補うアピール系の選択
曇りや雨といった光量の少ない天気では、朝夕マズメと同じようなカラーの選び方をします。
特に水が濁っている釣り場で、曇りや雨の場合、昼間であってもチャート系カラーが活躍する場面があります。光量不足を補うために、積極的にアピールしていく戦略が有効です。
一方、透明度が高く魚の活性があまり高くないようであれば、アピール力が少し控えめなコットンキャンディもおすすめです。
実際に曇天や雨天時の釣行では、コットンキャンディカラーで何度もいい思いをしています。派手すぎず地味すぎない絶妙なアピール力が、こうした条件にマッチするんです。

代表的なシーバスパターン別カラー攻略法

シーバス釣りには季節や状況に応じた様々なパターンがあり、それぞれに効果的なカラーが存在します。
これまでの釣行経験で蓄積したパターン別のカラー戦略をお伝えします。
バチ抜けパターンはブラピン(ブラック×ピンク)が最強の理由
春の風物詩であるバチ抜けパターンでは、ブラピン(ブラック×ピンク)が圧倒的な実績を誇ります。
バチ(ゴカイ類)は数が多すぎてルアーに気付いてもらいにくく、強い波動を出すルアーでは逆に食ってこないという特徴があります。
実際にバチ抜けシーズンの河口で釣りをしていると、他のカラーでは全く反応しなかった魚が、ブラピンに変えた瞬間に食ってくることが本当に多いんです。
バチ抜けは2月から6月頃まで続くロングシーズンなので、この時期はブラピンカラーのルアーをタックルボックスに必ず入れておきたいですね。
落ち鮎パターンはシルバー・ゴールド系で大型を狙う
秋の落ち鮎パターンでは、シルバー系やゴールド系のルアーが効果的です。
落ち鮎は体長15〜20cmの大型ベイトなので、それに合わせてルアーサイズも大きくする必要があります。同時にカラーも大型ベイトを意識したものを選択します。
| ベイトの状態 | おすすめカラー | 使用ルアー例 |
|---|---|---|
| 健康な落ち鮎 | シルバー・ナチュラル系 | 大型ミノー、ビッグベイト |
| 弱った落ち鮎 | ゴールド・チャート系 | バイブレーション、シンペン |
| 死に鮎 | ブラック系 | ワーム、ソフトルアー |
地元の大河川では、9月頃から落ち鮎パターンが始まりますが、この時期はランカーサイズのシーバスが狙える絶好のチャンスです。
実際に80cmオーバーのシーバスを仕留めた時も、シルバー系の大型ミノーでした。落ち鮎の群れに紛れ込ませるイメージで、自然な色合いを心がけています。
激戦区・スレ対策はみんなと違うカラーで差をつける方法
激戦区では毎日同じようなカラーのルアーが投げられているため、魚がカラーにスレることがあります。
そんな時は、一般的な使い分けとは対極に位置するカラーを入れてみることが効果的です。クリアが強い時にマットチャートを入れる、といった具合ですね。
みんなが実績カラーを投げている激戦区では、不人気カラーが意外な威力を発揮することがあります。特にブラック系は不人気カラーの代表格ですが、魚にとってはハイアピールなので捕食スイッチを入れる可能性があります。
実際に地元の人気ポイントでは、レッドヘッドやブラウン系など、普段あまり使われないカラーで釣果を上げることが多いです。
釣り人の心理として、「みんなが使っているカラー=よく釣れるカラー」と考えがちですが、激戦区ではその逆を行く発想も必要ですね。
ベイトサイズ別の小型・大型ベイトに合わせたカラー選択
ベイトのサイズに合わせたカラー選択も重要な要素です。
小型ベイト(シラス・小アジ)には透明感のあるクリア系、大型ベイト(イワシ・ボラ)には存在感のあるシルバー・ゴールド系といった使い分けを心がけています。
| 小型ベイト(3-5cm) | 中型ベイト(6-10cm) | 大型ベイト(11cm以上) |
|---|---|---|
クリア系が効果的 透明感でサイズダウン 自然な存在感 | シルバー系が基本 適度なフラッシング バランス重視 | ゴールド系で存在感 強いアピール力 大型魚を誘引 |
特にシラスパターンの時期は、クリア系のルアーが圧倒的に強いです。ショアジギングにおいても、ベイトがシラスの時にはクリア系が欠かせない必須カラーとされています。
釣果に直結する実践的カラーローテーション術

カラーの基本を理解したところで、実際の釣り場でどのようにカラーを使い分けるかが重要になります。
これまでの経験で培ったローテーション術をお伝えします。
初心者が最初に揃えるべき5つのカラー
シーバス釣りを始める方には、まずこの5色を揃えることをおすすめします。
| カラー | 主な用途 | 優先度 |
|---|---|---|
| ブラック | 夜釣り・濁り・困った時の最終兵器 | ★★★★★ |
| クリア | スレ対策・オールラウンド・満月夜 | ★★★★★ |
| シルバー | デイゲーム・イワシパターン | ★★★★☆ |
| チャート | マズメ・夜釣り・アピール重視 | ★★★☆☆ |
| ゴールド | 濁り潮・朝夕マズメ・大型ベイト | ★★★☆☆ |
この5色があれば、ほとんどの状況に対応できます。特にブラックとクリアは絶対に外せない2色です。
予算が限られている場合は、まずブラックとクリアから揃えて、徐々に他の色を追加していくのがおすすめです。
状況変化を読むカラーチェンジのタイミング
カラーローテーションで最も重要なのは、いつカラーを変えるかのタイミングです。
同じカラーで10〜15キャスト反応がない場合、または明らかに状況が変わった時(潮の変化、ベイトの動き、他のアングラーの釣果など)にカラーを変更します。
よくある間違いは、3〜4投で反応がないとすぐにカラーを変えてしまうことです。シーバスは気まぐれな魚なので、ある程度の粘りも必要です。
【ステップ1】基本カラーでスタート
その時間帯・水質の基本となるカラーから開始。10〜15キャスト様子を見る
【ステップ2】対極カラーに変更
反応がなければ、対極に位置するカラーに変更。アピール⇔ナチュラルの切り替え
【ステップ3】中間色で調整
それでもダメなら中間的なカラー(コットンキャンディなど)で微調整
【ステップ4】最終兵器投入
全て反応なしの場合、ブラック系やレッドヘッドなど特殊カラーを投入
1回の釣行で持参するカラーの組み合わせ方
実際の釣行では、想定される状況に応じて3〜5色程度を持参するのが現実的です。
全てのカラーを持参すると選択に迷ってしまうため、事前に戦略を立てておくことが重要です。
春のバチ抜け狙いの夜釣り
サブ1:クリア(スレ対策)
サブ2:レッドヘッド(定番夜色)

まとめ:カラー選択をマスターして釣果アップを実現
シーバスルアーのカラー選択について、科学的根拠から実践的な使い分け方法まで詳しく解説してきました。
最も重要なポイントは、ブラックとクリアの2色をマスターすることです。この2つがあれば、ほとんどの状況で釣果を上げることができます。
時間帯や水質、天候といった条件に応じてカラーを使い分けることで、確実に釣果は向上します。ただし、カラーにこだわりすぎるよりも、まずは基本の2色で経験を積むことが重要です。
長年の釣行経験から言えるのは、カラーは確実に釣果に影響するということ。しかし、それ以上に大切なのは、選んだカラーに自信を持って集中して投げ続けることです。
この記事で紹介したカラー選択術を参考に、ぜひ皆さんの釣果アップに役立ててください。きっと今まで釣れなかった場面でも、魚を手にできるようになるはずです。